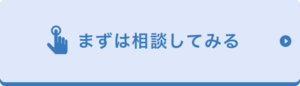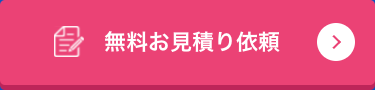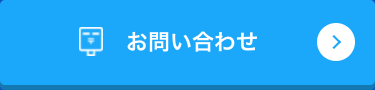新築やリフォームの話でよく耳にする「気密性」。でも実際には「どういう意味?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、気密性は住宅の性能を大きく左右する、とても重要な要素です。この記事では、気密性の基本から、高気密住宅のメリット・デメリット、C値、断熱性との関係までをわかりやすく解説します。この記事を読めば、気密性に関する理解が深まり、理想の住まいを実現するための第一歩を踏み出せるでしょう。
気密性とは?住宅性能を左右する秘密

「気密性」とは、建物内部の空気がどれだけ漏れにくいかを表す性能のことです。隙間が少ないほど気密性が高いと評価されます。この性能は、住宅の快適性、省エネ性、耐久性にも深く関わっています。
気密性と断熱性の違い
混同されやすい「断熱性」との違いを整理しておきましょう。
- 気密性=空気の出入りをどれだけ防げるかを示す性能。
- 断熱性=熱の伝わりをどれだけ抑えられるかを示す性能。
断熱材だけを厚くしても隙間が多ければ効果は薄れます。逆に気密性を高めても断熱材が不十分だと室温を保てません。両者は補い合う関係にあり、バランスが重要です。
気密性の定義

気密性とは、住宅にどれだけ隙間があるか(=隙間の少なさ)を数値で示したものです。具体的には、家全体の隙間面積を床面積で割った「C値」という指標で評価されます。C値が小さいほど、気密性が高いと判断されます。この隙間には、意図的に設けられた換気口だけでなく、窓やドアのわずかな隙間、壁と床の継ぎ目なども含まれます。
なぜ気密性が重要なのか?

気密性は住宅の様々な性能に影響を与える重要な要素です。断熱性能を最大限に活かし、計画的な換気を可能にし、冷暖房効率を高めることで省エネにもつながります。さらに外気中のホコリや花粉、有害物質の侵入を防ぎ、健康的で快適な室内環境を維持するうえでも欠かせません。
気密性が住宅にもたらす影響
断熱性との関係
断熱材は熱の移動を抑え、室内の温度を快適に保つ役割を果たします。しかし気密性が低いと、隙間から外気が侵入して断熱材の効果が損なわれ、暖房効率の低下や光熱費の増加につながります。
断熱材にはいくつかの種類があります。
- グラスウール:安価で施工しやすいが湿気に弱い。
- ロックウール:耐火性が高く、音も遮りやすい。
- セルロースファイバー:新聞紙などを再利用したエコ素材で、防音性も高い。
- ウレタンフォーム:発泡して隙間を埋めるため、気密性を確保しやすい。
気密性と断熱性をセットで考えることで、これらの性能を最大限に発揮できます。
換気との関係
高気密住宅では「計画換気」が欠かせません。気密性が低いと、換気システムを稼働させても隙間から空気が出入りしてしまい、計画通りの換気ができません。その結果、湿気や汚れた空気がこもりやすく、結露やカビの原因になることがあります。
高気密であれば換気システムがしっかり働き、常に新鮮な空気を取り込める環境を保つことができます。
省エネ効果
高い気密性は、冷暖房効率を向上させ、エネルギー消費を抑えます。冬は暖めた空気が逃げにくく、夏は冷房した空気が外に漏れにくいため、少ないエネルギーで快適な暮らしを続けられます。光熱費の削減に加え、環境負荷の軽減にもつながります。
C値とは? 気密性を測る指標

C値の定義
C値(相当隙間面積)とは、住宅の気密性能を表す指標で、建物全体の隙間の合計面積を延床面積で割った数値です。単位は cm²/m²(平方センチメートル毎平方メートル)で表されます。この数値が小さいほど隙間が少なく、気密性が高いことを意味します。
C値の基準と目安
かつては新築住宅にC値基準が設けられていましたが、現在は法律上の義務はありません。それでも、高気密住宅を建てるうえでC値は重要な指標です。
C値を生活イメージで理解する
例えばC値2.0とは、延床面積100㎡の住宅に、はがき1枚分(約200cm²)の隙間がある状態です。C値1.0であれば、その半分程度の隙間しかありません。
数値だけでは分かりにくい性能も、日常的な大きさに置き換えると理解しやすくなります。
C値の測定方法
C値は専門業者による気密測定で算出されます。建物の開口部を塞ぎ、換気扇で減圧した状態で隙間から漏れる空気量を測定し、それを床面積で割ってC値を算出します。測定結果は住宅の性能を客観的に評価する重要なデータとなります。
高気密住宅のメリットとデメリット

メリット:快適な住環境、省エネ効果
高気密住宅の最大のメリットは「快適な住環境」です。隙間風がなく、室内の温度が一定に保たれるため、冬は暖かく夏は涼しい空間を実現できます。
例えば冬でも素足で過ごしやすい、冷暖房の効きが早い、といった生活面での実感につながります。また、計画換気が可能になるため、花粉やPM2.5の侵入を抑え、ヒートショック予防など健康面でも安心です。
さらに、省エネ効果も大きな利点です。冷暖房効率が高まり、光熱費の削減につながるうえ、環境への負担軽減にも貢献できます。
デメリット:結露、乾燥、換気、コスト
一方で、高気密住宅には注意点もあります。湿気がこもると窓や壁内に結露が発生しやすく、放置すればカビや建材の劣化につながります。逆に冬は空気が乾燥しやすく、加湿器や調湿建材の活用が必要になることもあります。
また、換気システムが十分に機能しない場合は空気がよどみ、ホルムアルデヒドなどによるシックハウス症候群のリスクも高まります。適切な換気計画とメンテナンスは欠かせません。
さらに、施工精度が求められるため建築コストが上がる傾向があり、換気システムの維持費もかかります。費用面も含めた総合判断が重要です。
気密性を高めるには? 具体的な方法と注意点

施工方法
壁や天井、床の接合部を丁寧に処理し、気密シートや気密テープで隙間を確実に塞ぐことが重要です。窓やドアも気密性の高い製品を選び、専門業者による精度の高い施工で性能を確保しましょう。
隙間をなくす対策
配線や配管まわり、換気扇の設置部分などは隙間ができやすいため、気密シートやシーリング材を使って入念に処理する必要があります。こうした細部の対策が住宅全体の気密性向上につながります。
気密測定と保証
気密測定を行えば、施工の精度や隙間の有無を客観的に確認できます。結果はC値として数値化され、不備の発見や換気システム調整にも役立ちます。さらに、施工会社や第三者機関が測定結果を保証する仕組みがあれば、安心感も高まります。
高気密住宅を選ぶ際の注意点

換気システムの選び方
高気密住宅では、第一種換気・第二種換気・第三種換気のいずれかを選びます。
- 第一種換気:給気・排気を両方とも機械で行います。室温を一定に保ちやすく、熱交換換気装置を組み合わせれば省エネ効果も期待できます。
- 第二種換気:給気を機械、排気を自然に行う方式です。室内の気圧が高くなるため、外気の侵入を防ぎやすいのが特徴。ただし一般住宅ではあまり使われず、クリーンルームなど特殊な施設で多い方式です。
- 第三種換気:給気は自然、排気を機械で行います。設置コストが低くシンプルですが、外気の影響を受けやすく、冷暖房効率は落ちやすい傾向があります。
こうした違いを理解して、住宅の性能や暮らし方に合った方式を選ぶことが重要です。
断熱性能とのバランス
気密性と断熱性は互いに補完する関係です。断熱材の種類や厚さ、窓の性能などを適切に選ぶことで、快適性と省エネ性をさらに高められます。
設計段階からの配慮
気密性を確保するには、施工だけでなく設計段階からの計画も重要です。換気経路の設計、断熱材の配置、配管・配線の取り回しなど、設計段階での工夫が施工後の性能に直結します。設計と施工が一体となった計画が、高気密住宅を成功させる鍵です。
専門家のアドバイス
設計段階から気密性を考慮できる専門家のサポートを受けると安心です。施工事例や評判を確認し、信頼できる業者を選びましょう。複数の見積もりを比較して検討することも大切です。
まとめ:気密性の理解を深めて理想の住まいを実現しよう

気密性は住宅の快適さ、省エネ性、耐久性を大きく左右する要素です。この記事では、気密性の定義、断熱性との違い、C値の意味、高気密住宅のメリット・デメリットについて解説しました。
高気密住宅を建てる際には、換気システムの選定や断熱性能とのバランス、設計段階からの配慮が欠かせません。さらに第三者機関による測定・保証を取り入れることで、より安心して計画を進められます。
気密性の知識を活かして、快適で健康的な住まいづくりにぜひ役立ててください。
快適で省エネな住まいづくりは一二三工務店へ
気密性は住まいの快適さや光熱費に直結する大切な性能です。
「自宅の気密性を高めたい」「高気密・高断熱の家づくりを相談したい」とお考えの方は、ぜひ一二三工務店にご相談ください。